ドキュメンタリーが私たちに見せてくれるもの
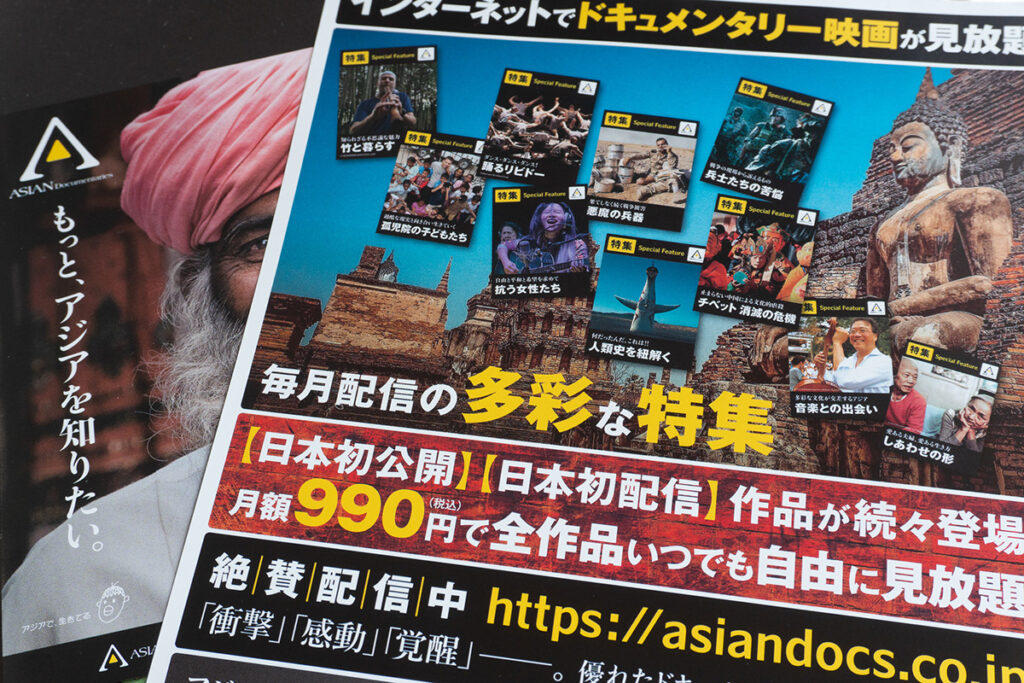
――それでもドキュメンタリーを事業にしなければと思ったのはなぜですか。
私たちは、日本と海外との違いについて、もっと知り、学び、考える機会が必要だと思ったのです。
以前、米国との共同制作で「硫黄島の戦い」のドキュメンタリーを制作しました。両国共同で撮影して、編集はそれぞれの国で編集。同じ映像素材で中身が全く違う2つの作品ができるという、自分にとって初めての経験でした。テーマは「日米は和解したのか」。戦後70年が過ぎ、日米は安全保障のパートナー、同盟国として成り立っていますが、私がそこで感じたのは、戦争に対する両国の意識の差でした。
日本の戦争ドキュメンタリーは暗く悲しい音楽が流れます。一方、米国は勇壮なメロディです。まずそれに度肝を抜かれました。同じ素材で制作しているのに、戦勝国と敗戦国の違いを思い知らされました。戦争に関わったことについても、日本では「国のために戦ったことは悲劇」であるのに対して米国では「誇り」。価値観が全く違います。捕虜の扱いも、日本では「恥」「万死に値する」「捕虜になるくらいなら死ね」と言われたのに対して、米国では、捕虜になるまで健闘したという「名誉」ですから、180度違います。戦争における名誉とは、日本では「戦死すること」ですが、米国では「生きて帰ってくること」。日本では戦争は「悪いこと」ですが、米国では「国益を守るための手段」。戦勝国と敗戦国の意識の差は、戦後70年たっても明確に残っています。
米国に対してだけではなく、日本人が当たり前と思っていることが、海外では当たり前ではないのです。それを日本人が知らなければならないと思うのです。